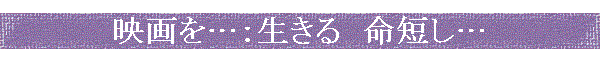「午前十時の映画祭 7」では、入場者数が一番多かった。年代も若い人、中年の人、われわれ世代の三層に分かれていたことが、第一印象である。
役所勤めの渡辺(志村
喬)は、胃癌で余命わずかと知る。いまと違って、癌は死の宣告となり、絶望感にさいなまれ、家族にも打ちあけられない。
30年間の勤めは可もなく不可もなく、市民課長としての仕事にもやりがいを感じない毎日を過ごしている渡辺。その彼が、役所を欠勤して大枚の5万円(昭和27年)を貯金から引き出して、精一杯の思いを試みる。しかし、いずれも納得がいかず、悶々とした日を送る。そんな折、玩具工場へ転職する部下(小田切みき)の若さと生き生きとした姿に、“生きる希望”を見出す。彼女と一緒にいる時が「楽しい」と悟る渡辺の心境は、いまの私にはよくわかる。
“ 希望
”を見出した渡辺は、市民から出されていた湿地帯の公園化に向けて、一大決心をする。さまざまな課との問題を乗り越え、公園はできあがる。そんな冬の日、公園のブランコで一人命を終える。
黒澤明
監督はここで終わらせず、渡辺の希望や信念を伝えるために、「通夜の場面」を設ける。劇中、部下の職員 左卜全が「う〜ん」「おかしい」と何度もつぶやき、渡辺の思いを観衆にぶつける。「生きる」という意味を、私は自分に問いかけながら鑑賞した。「生きる」とは、“
希望を見出すこと
”ではないだろうか。天命を知れば、強く深く生きられる。
しみじみとした温かい気持ちがわき、快い足取りで出口に向かった。
(報告:瀬山宏昭、写真:熊谷康夫) |

海鮮料理「はなの舞」で昼食 |